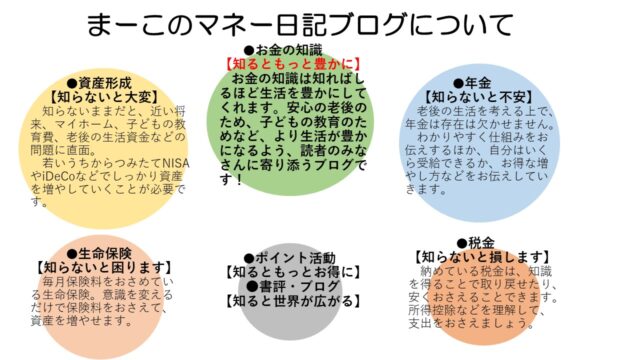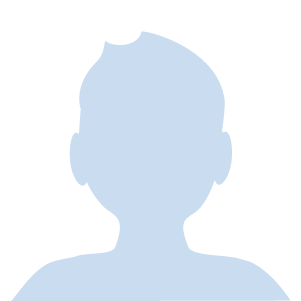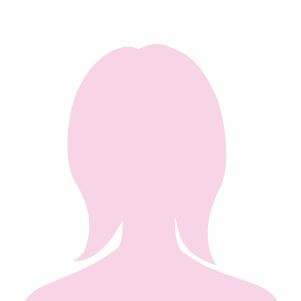2023年末でジュニアNISAは終了。
この終了によって「子どもが18歳になるまで引き出せない」という引き出し制限がなくなり、ジュニアNISAは、2023年末までの期間限定の“つみたてNISA”になりました。
非課税の投資枠が拡大するため、つみたてNISAをすでに始めている方や学資保険を検討している方、金銭的に余裕がある方はジュニアNISAをぜひとも有効活用しましょう。
こんにちわ!まーこ(@maakomoneydiary)です。
今回の記事のテーマは「ジュニアNISA」です。
はじめに結論をお伝えいたします。
●2023年末でジュニアNISAは終了
●終了により「子どもが18歳になるまで引き出せない」というデメリットがなくなる
●このデメリットが解消されたことにより、ジュニアNISAは、2023年末までの期間限定のNISAに(集中的な投資が可能に)
●いつでも引き出せる上、子どもが18歳まで非課税で運用出来てお得
●非課税の投資枠が拡大するため、つみたてNISAをすでに始めている方や学資保険を検討している方、金銭的に余裕がある方はジュニアNISAを有効活用しましょう。
1 ジュニアNISAが期間限定のつみたてNISAに
2024年1月から新NISAに
2020年3月の税制改正で所得税法の一部の改正が成立しました。
これによって2024年1月1日から、NISA制度が大きく変わります。
今回の制度改正のメイン部分は、これまでの一般NISAが、1階部分をつみたてNISA(年間20万円まで)、2階部分を一般NISA(年間102万円まで)という2階建て構造の「新NISA」になることです。
詳細については、「【制度改正】NISAが2024年から大きく変わります。新NISAのポイントを説明」をご覧ください。

そして続けて、
●つみたてNISAが新規に投資できる期間を2042年末に延長。
●ジュニアNISAは、2023年末で終了する。
という内容も発表されました。
ジュニアNISAの「引き出し制限解除」に注目
「新NISA」については、1階部分につみたてNISAを構成したことで、安定的な投資をより強調する形となりました。
ですが、むしろ複雑さが増した感があり、あまり魅力的な改正とは思えません。
その一方で、ジュニアNISAに関する「2023年に終了」「2024年から引き出し制限解除」という内容、特に「引き出し制限解除」はとても魅力的な改正なのです。
引き出し制限解除、つまり引き出しが自由にできるという意味です。
「NISA」や「つみたてNISA」と全く同じ使い勝手となるのです。
言い換えるならば、「ジュニアNISAは、2023年末までの3年間限定(2021年1月から始めた場合)のNISAやつみたてNISAになった」と言えるのです。
ジュニアNISAが不人気だった理由
他のNISAと比べて、ジュニアNISAが圧倒的に不人気だった理由が、この「引き出し制限」にありました。
「引き出し制限」とは、原則として子どもが18歳になるまで引き出すことができない、というものです。
これらを含めて、ジュニアNISAの現行制度と制度改正後の内容は次のようになります。
| 現行制度(~2023年) | 改正後(2024年1月~) | |
| ジュニアNISA | ●口座開設者:日本に住む0歳から19歳 ●口座管理・運用者:親、祖父母 ●年間80万円まで非課税 ●対象商品:株式、株式投信など一般の投資商品全般 ●投資可能期間:5年間 ●原則、口座開設者が18歳なるまで引き出すことはできない |
●2023年末で制度終了 ●新規の口座開設は2023年末まで ●「18歳まで引き出せない」という引き出し制限は解除 ●子どもが20歳になるまで、金融商品を非課税で持ち続けることができる |
具体的に、18歳まで引き出すことができない「引き出し制限」によって次のようなデメリットが生じていました。
デメリット
●投資可能期間が5年であるため、例えば子ども1歳の時にジュニアNISAを開始したら6歳時に投資が終了。6歳から18歳になるまでの12年間待たなければならないこと
●0歳~18歳になるまでの間に引き出すと課税されてしまい、お得感がないこと
●子どもが18歳になるまで引き出せないため、中学や高校時の教育費に対応できないこと
●ジュニアNISAは、大学の入学金及び授業料を想定しているものの、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は払い出せず、そのため、高校3年秋の推薦入試合格後の入学金や予備校代に対応することができないこと。
制度が改正される2024年1月以降は、こうしたデメリットが解消されるということです。
2 期間限定のため、ぜひ有効活用を
今(2021年1月)からジュニアNISAを開始すれば、年間80万円×3年間=最大240万円+運用益を獲得することができます。
最大240万円が、10数年後には500万円以上の資産になる可能性があるのです(しかもいつでも引き出し自由)
そしてその後は、いつでも引き出すことができる資産となります(非課税期間は子どもが20歳になるまで)。
ジュニアNISAで増やした資産は、いつでも対応可能な教育費に充当できるほか、老後資金の下地としても活用できます。
こんな方はぜひジュニアNISAを
デメリットがなくなった「ジュニアNISA」をぜひともおすすめしたい方々は次のようになります。
●つみたてNISAの年間40万円枠では少し物足りなさを感じている人
●学資保険への加入を検討している人
●銀行に必要以上の預金残高がある人あるいは今の生活で金銭的な余裕がある人
つみたてNISAを始めている人は、3年間限定で年間120万円(つみたてNISA:40万円、ジュニアNISA:80万円)の非課税の投資枠を確保することができます。
そのため、40万円枠で少し物足りなさを感じている人はぜひともジュニアNISAの導入も検討しましょう。
学資保険は、子どものケガや病気に備える保障機能があるものの、貯蓄機能だけを見てみると、「コスパの悪い投資商品」と言うことができます。
学資保険に加入して毎月一定の保険料を積み立てていくのであれば、それよりもはるかにコスパの優れたつみたてNISA、そしてジュニアNISAを始めることをおすすめします。
学資保険の詳細については、本ブログをご参照ください。
銀行の超低金利によって、銀行に預けていても資産を増やすことはできません。
生活費などの必要最低限を預金して(だいたい生活費の6か月分と言われています)、それ以外はつみたてNISAやジュニアNISAにまわしていくことで、資産をしっかり増やすことができます。
最後にポイントをまとめます。
●●2023年末でジュニアNISAは終了
●終了により「子どもが18歳になるまで引き出せない」というデメリットがなくなる
●このデメリットが解消されたことにより、ジュニアNISAは、2023年末までの期間限定のNISAに(集中的な投資が可能に)
●いつでも引き出せる上、子どもが18歳まで非課税で運用出来てお得
●非課税の投資枠が拡大するため、つみたてNISAをすでに始めている方や学資保険を検討している方、金銭的に余裕がある方はジュニアNISAを有効活用しましょう。
「NISA」=将来に向けて資産をしっかり確実に増やすことができます。
今回の記事でご紹介した「ジュニアNISA」も、もちろん資産形成・運用に効果的です。
ジュニアNISA以外にも、NISAやつみたてNISAも、将来に向けて資産をしっかり確実に増やすことができます。
NISAとつみたてNISAの2つを併用することはできませんが、ジュニアNISAとの併用はOKです。
「NISA」について、下記の関連記事でわかりやすく説明しています。
ぜひこの機会に始めましょう!
●NISAについて
1.「【まだ始めてない方は必見】積立NISAをおすすめする背景と理由」
2.「積立NISAの概要とおすすめ銘柄」
3.「【初心者向け】まずはこれ!今すぐ始めたい4つの資産形成」
4.「【併用が正解】積立NISAとiDeCo、やるならどっち?20年後をシミュレーション」
5.「【1年やるとこうなる】つみたてNISAとiDeCoの実績を公開します」
6.「【つみたてNISA】よく見るインデックス投資とは?おすすめをご紹介」
7.「【制度改正】NISAが2024年から大きく変わります。新NISAのポイントを説明」
8.「【廃止後どうする?】ジュニアNISAが期間限定の“つみたてNISA”に。ぜひ有効活用を」
9.「【20年後どうする?】つみたてNISAの受け取り方は保有か売却の2パターン」
10.「【NISA】ロールオーバーとは?5年後をシミュレーションしてわかりやすく説明」
11.「【廃止だけど申込増】ジュニアNISAで実際に商品を購入するまでの流れ(約1か月)」
12.「【NISA】よく見る「ETF」って何?投資信託との違いは?オススメはどっち?」
13.「【つみたてNISAは20年後暴落なら大損?】よくある勘違いをわかりやすく説明」
14.「【ジュニアNISA】子どもが18歳までどれくら貯まる?シミュレーションした結果」
15.「【忙しい人限定】つみたてNISAが3分で理解できる一問一答」